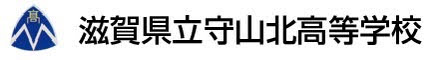信楽の最先端技術が文化財を活かす

美術Ⅰ(1年生)の「文化財」をテーマとした授業の4回目は、甲賀市信楽町にある大塚オーミ陶業株式会社の野口歩実さんに講義をして頂きました。同社は、世界の建築物の壁画や名画を陶板で再現して、徳島県の大塚国際美術館に展示していることで知られていますが、セラミック(陶土)を用いた様々な製品開発や事業を行う企業です。特に、古い美術品や壁画などをセラミックで再現し保存する「セラミックアーカイブ」に取り組まれています。
講義では、滋賀県内の寺院の掛け軸を陶板で立体的に作られたことや、高松塚古墳の壁画絵画を再現されたことを、その模型なども用いて説明してもらいました。実際には触れない文化財のレプリカを作ることの意義を話していただきました。
文化財の保存と活用を最先端の技術で可能としている様子から、その根本にある社会的な意義や使命感、テクノロジーと人の力でできることなど、新たな視点が得られたのではないでしょうか。
【生徒の感想より】
・自分にとっては食器やタヌキの置物でしたが、今日の講義で「やきもの」に対してのイメージがガラッと変わりました。
・機械でできないことは、最後は人の手作業で大事に作られているんだなあと思った。
・それを「残したい」「知ってほしい」という気持ちを大事にされていて、ステキなお仕事だと思った。
・普通の美術作品は実施に手で触れることが難しいけど、陶芸で作ったものであれば手で触れて感じられる。目が見えない人も楽しめるようにという考え方を聞いて、より関心が深まった。